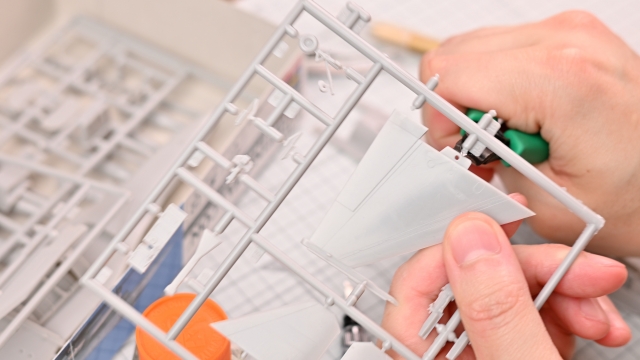こんにちは。
毛利まさるです。
「いつまでこんな毎日が続くんだろう…」と、ため息をついたことはありませんか?
目覚ましの音で無理やり起きて、満員電車に揺られ、やっと仕事を終えたと思ったら、また翌日も同じことの繰り返し。
「もっと楽に生きられないかな」「この負担、いつまで続くんだろう」
そんなふうに感じたこと、一度や二度ではないと思います。
実を言うと、私も同じでした。
特に社会人になって数年目、慣れない仕事、人間関係、終わらないタスク。
心の中で「これはいつか終わるんだ」と思っていたから耐えていた。
でも、現実はそう甘くはない。
気づいたんです。「これ、終わらないかもしれない」と。
負荷は“異常”ではなく、“生活の一部”と考える
ここで、一つ提案です。
「負荷は異常なものではなく、日常の一部である」と捉えてみてはどうでしょうか。
学生から社会人になったとき、急に自由がなくなってびっくりしませんでしたか?
でも、数年経った今はそれが普通になっていませんか?
当時は「こんな生活やってられない」と感じていたはずです。
それが、今は慣れてしまっている。
つまり、人は負荷に“順応”できる生き物なんです。
この「負荷は今だけ」という考えをやめて、「これが生活のベース」として捉える。
すると不思議なことに、気持ちが軽くなります。
なぜなら、「耐えるべきもの」ではなく「付き合うべきもの」として見られるようになるからです。
未来に希望があるか?がすべてのカギ
私が何度も自分に言い聞かせていた言葉があります。
それは、「未来に希望があれば、人は今を耐えられる」ということ。
逆に言うと、今が辛いと感じるのは、
・未来に何も変わらないと思っている
・変わったとしても意味がないと思っている
そうした無力感に覆われてしまっているから。
だったらどうすればよいんでしょうか?
答えはシンプルです。楽しい未来を想像するのです。
現実逃避ではありません。
「こうなったらいいな」と思える未来像を持つことで、今の行動に意味が宿ります。
負荷を“敵”ではなく“共に歩む仲間”と考える
ここが本質です。
私たちはつい「負荷を減らすこと」ばかりに意識を向けます。
もちろん、改善や効率化は大切です。しかし、負荷そのものと戦う姿勢だけでは疲弊します。
映画『ショーシャンクの空に』で、アンディはこう語ります。
“Hope is a good thing, maybe the best of things.”
(希望はいいものだ、たぶん最高のものだ)
負荷はなくならない。
ならば、その中でどうやって“希望を持てる自分”でいるか。
その視点が、あなたを救ってくれます。
心が折れそうなときに試してほしい3ステップ
- 今の状況を受け入れる 「もう嫌だ」と思ったとしても、「これが今の自分の生活なんだ」とまずは受け止めてみる。
- 改善できることを一つ探す 例えば、10分だけ早く寝る。通勤中に好きな音楽を聴く。そういう小さな工夫を積み重ねる。
- 未来の“いいイメージ”を持つ 「こんな働き方ができるようになりたい」「こんな生活が送れたら嬉しい」 そんな“光”を一つ持つだけで、今日の負荷に意味が宿る。
最後に伝えたいこと
「負荷があるからダメなんじゃないんです。負荷があるからこそ、自分は今成長している」
そう思えるようになると、世界の見え方が変わります。