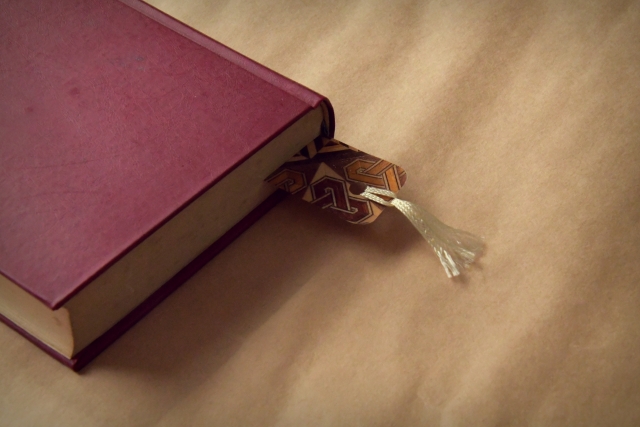こんにちは。
毛利まさるです。
なんとなく観て終わっていませんか?
映画や漫画を観終わった後、「面白かったなぁ」で終わってしまうこと、ありませんか?
もちろん、それだけでも娯楽としては十分なのです。しかし、もしそこから一歩踏み込んでみたら?
その作品の背景、時代、モチーフになった歴史や人物。
そこに目を向けることで、あなたの世界の見え方がぐっと広がっていきます。
そしてこれは、実はただの趣味ではなく、立派な仕事術にもなるのです。
なぜなら、深掘りする癖をつけることで、あなたの“情報を扱う力”が高まっていくからです。
「履修する」という新しい観方
今、「履修」という言葉がSNSでよく使われるようになりました。
あるアーティストの新作が出たら、そのルーツである過去の作品や関連する背景を「履修する」と言うのです。
この行動はまさに、仕事術としての情報収集・分析・関連付けのトレーニングにぴったりです。
たとえば、『鬼滅の刃』という作品を観たとします。
敵キャラである鬼舞辻無惨は、実は日本の伝承に登場する「酒呑童子」がモデルだと言われています。
さらに、上弦の鬼たちの背景には、結核や栄養失調など、病気にまつわる現実的なモチーフが込められています。
このようなことを知った上で作品をもう一度観ると、受け取る印象や感情の深さがまったく変わってくるのです。
「履修」がもたらす仕事への好影響
作品を深く観る力は、日常業務でも大きな武器になります。
たとえば、プレゼンで企画の背景を語るときや、商談で相手の業界を理解するとき。
ただ言われたことをやるのではなく、文脈や背景に目を向ける人ほど信頼されやすくなるのです。
これは仕事術として非常に重要な力です。
「なぜこの人はこの提案をしているのか?」
「このサービスはなぜ今注目されているのか?」
そうしたことを想像し、関連情報を「履修」することによって、表面的な理解から抜け出すことができます。
そして、それを繰り返すうちに、「自分の視点」が育ってきます。
深掘りは、共感と洞察につながる
何かを深く知ろうとすることは、相手を理解しようとすることとよく似ています。
つまり、深掘りの姿勢は、人間関係やコミュニケーションにも役立つということです。
たとえば、相手が話してくれた好きな映画や趣味について、あなたがその背景を知っていたとしたらどうでしょう?
「そこまで知ってるんですか?」と、相手の心に一気に距離を縮めることができます。
これは、ただ知識があるだけでなく、「あなたの世界に興味を持っていますよ」というメッセージにもなるのです。
だから、深掘りすることは、単に“知ってる人”ではなく、“わかってくれる人”になれる方法でもあるのです。